看護体制って、実はこんなに違う
施設を選択する基準、施設の豪華さや設備だけに目がいっていませんか?実は看護とリハビリの体制・内容にも大きな違いがあるんです。
1.「看護師常駐=安心」とは限らない?

「看護師が常駐しています」と聞くと、「それなら安心」と思う方は少なくありません。でも実は、“常駐”という言葉の定義や実態には幅があります。たとえば、日中のみの常駐なのか、夜間も含めて24時間体制なのか。さらに、常駐している人数や役割も施設によってバラバラです。
ある施設では看護師が日中1人だけ勤務し、他の業務と兼任している場合もあります。一方で、複数名が交代制で常時待機しているところもあり、医療連携の体制や緊急時の対応にも差が出てきます。
「何かあったらすぐに対応してもらえるのか」「医療機関との連携がスムーズか」など、看護体制の“深さ”を見極めることが、長い目で見て安心できる施設選びにつながります。
施設見学では、「看護師は何人いるか」「どの時間帯まで対応可能か」など、具体的に質問してみると良いでしょう。
2. リハビリの内容と頻度に大きな差が

介護施設では、日々の生活を支えるリハビリが非常に重要です。ただし、「リハビリができます」と書かれていても、その内容にはかなりの開きがあります。
たとえば、機能訓練指導員が週に1回だけ来てストレッチをする程度の施設もあれば、毎日理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が常駐していて、個別のプログラムに基づいた本格的なリハビリを受けられる施設もあります。さらには、専用のマシンやトレーニングルームを備えているところも。
「寝たきり予防」や「歩行能力の維持」は、入居後の生活の質(QOL)を大きく左右します。現在は元気でも、将来的な変化を見越して、リハビリの体制にも注目しておくことが大切です。
3. 医療連携と“できること・できないこと”を確認しよう
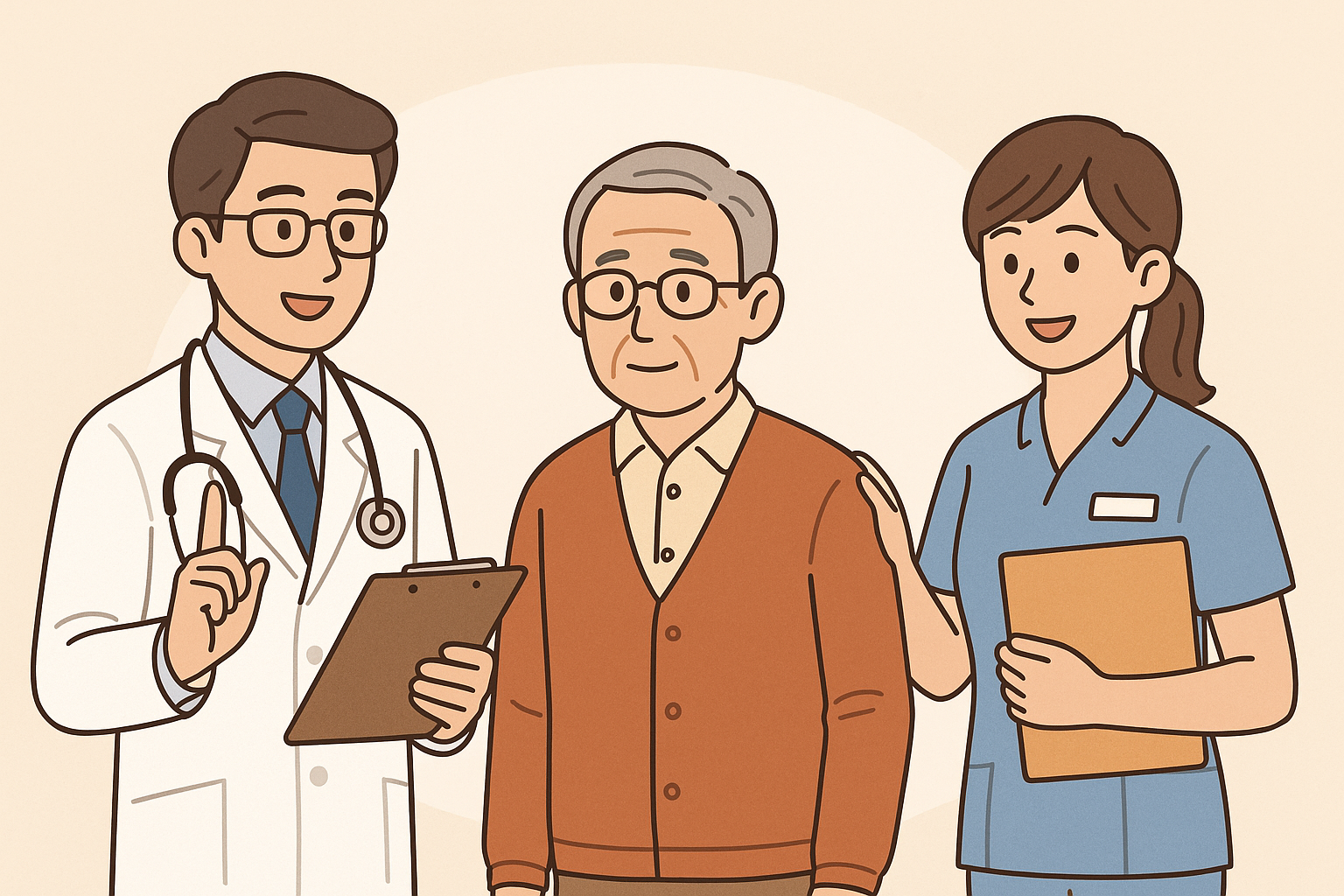
看護師がいても、すべての医療行為が可能なわけではありません。実際には「胃ろう」「インスリン注射」「吸引」などの対応可否が施設ごとに異なります。医療連携先のクリニックや訪問医の対応範囲によって、可能なケアに制限が出ることもあります。
また、看取り対応についても施設によって温度差があります。「最期まで見てもらえると思っていたのに、途中で病院に転院することになった」という話は意外と多いんです。事前に、終末期の方針や医療面での対応範囲について確認しておくと安心です。
入居後に「こんなはずじゃなかった」とならないように、自分たちの希望や将来的な医療ニーズに応じた体制が整っているかどうかを、あらかじめチェックしておくのがおすすめです。